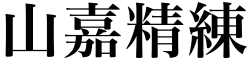きしろの水引

日本の儀礼や贈答文化には、御中元や御歳暮、冠婚葬祭に用いられる水引があります。
関東から京都へ越してきた弊社社員が、京都の仏事で『きしろの水引』を初めて知った時、水引の儀礼にも地域によって違いがあることに興味を持ち、意味や成り立ちを調べていく中で、日本料理店「きじま」様の慶事コラムに、水引の歴史が詳しく書かれていて勉強になったと、社内で話をしてくれました。
伝統美を感じさせる水引の美しい結びもさることながら、色彩の意味や成り立ちについても初めて教わるお話で、 ここにご紹介させていただきます。
::::::::::::::::::::::::::::::引用はじめ::::::::::::::::::::::::::::::
水引の起源
慶弔いずれの場合も、祝儀袋やかけ紙には「水引」を掛けます。
水引の起源は、飛鳥時代に遣隋使(けんずいし)とともに来日した隋(ずい)の使者の贈呈品に結ばれていた、
紅白の麻ひもであったといわれます。その後、宮中への献上品に紅白の麻ひもを結ぶ習慣が広まり、
庶民にも贈答が盛んになった江戸時代に日本独特の文化として定着しました。
水引の色わけ
水引は古代日本においては神事に供えられる供物を束ねる紐として用いられ、
神聖で汚れのない色として白一色が用いられていました。
現在のように色分けされるようになったのは、日本古来の「行事・まつりごと」に用いられていた
衣装装束の色分けと、古代中国より伝来した五行説の五原色が起源となっていると言われています。
::::::::::::::::::::::::::::::引用おわり::::::::::::::::::::::::::::::
五行説とは万物の全てが五つの元素つまり、木・火・土・金・水から成り立ち、互いに影響を与え合い、生滅盛衰によって天地万物が変化し循環する考え方であるそうです。
五つの元素を表す季節や色が決められており、木は春で青、火は夏で紅、土は土用で黄、金は白で秋、水は冬で黒となっていて、五行の色と四季を合わせた、青春、朱夏、白秋、玄冬といった言葉の元だそうです。
所説あるようですが、五行説に加えてさらには陰陽の考え方を学ぶと、有職故実、式典儀礼、伝統装束の色づかいへの理解が深まりそうです。
そして、主に仏事に使われる黒白の水引は、皇室で使われる玉虫色の紅水引が、一見すると黒白に見まごうことから、間違えないよう、京都に近い文化圏では仏事に黄白の水引が使われてきたようです。
水引について、長野県飯田の木下水引様のWEBサイト が大変勉強になります。
現代では、量産されている水引の場合に、近代的な製法に移り変わったものもあると思いますが、木下水引様が 皇室へ納めておられる紅水引は、伝統的な手法によるもので、着物の引き染めのようにして色を染めておられる ようです。紅水引の職人技が動画で公開されています。
紅と黒が関係の深い色同士であることも、絹糸の染めと似ていて興味深いです。
古代から受け継がれてきた水引は、日本が誇る文化です。